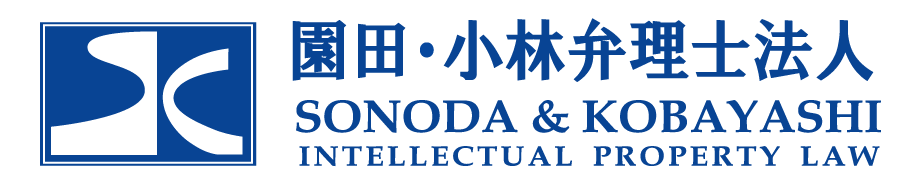2025年06月30日
令和7年5月29日に公布された「特許・実用新案審査ハンドブックの改訂」について、翻訳文に関する当所の見解を掲載いたします。※
「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂(「逐語訳による翻訳文」について)
特許・実用新案審査ハンドブックに、2025年5月29日の改訂で、「逐語訳による翻訳文でない場合の取扱い」が追加(第VII部 第2章 外国語書面出願の審査 7202)されました。審査基準が「特許法や関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたもの」であり、法律・規則ベースで遵守すべき枠組みに沿った位置づけであるのに対し、審査ハンドブックは、「審査官が審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項をまとめたもの」であり、審査官が審査を行う上での方針やスタンスを、あくまで一般的に推奨される形として示したものであって、場合によっては出願人に義務を課すべきでは無いものも含まれている可能性が考えられる類のものです。今回の改訂では、外国語書面出願・外国語特許出願の翻訳文について新たに項目が設けられ、
「この翻訳文は逐語訳による翻訳文(外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って翻訳したもの)である必要はない。」
と明記されました(下線は弊所による。以下同じ)。
この改定は、2015年9月30日まで運用されていた日本の特許審査基準の、
「第36条の2第2項に規定する翻訳文としては、日本語として適正な逐語訳による翻訳文(外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文)を提出しなければならない。」
という規定(現在は削除)を見直し、現行の
「審査官は、外国語書面が適正な日本語に翻訳された翻訳文(以下この章において「仮想翻訳文」という。)を想定し、明細書等がその仮想翻訳文に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正がその仮想翻訳文との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断する。」
という規定へ修正を行うことにより、ともすれば出願人を代理する日本国内の代理人が手掛ける翻訳の際の留意事項として関係法令で求められる適正な範囲を、審査官向けに「審査ハンドブック」の中で明示的に示すとともに、審査過程で生じる齟齬の解消を図るためにする改訂であると、弊所は理解しています。
上記改訂は、審査官に対して、外国語書面出願の審査対象である、原文新規事項の検討という場面における厳守すべき原則を示したものではありますが、振り返ると、制度元来の趣旨:外国語書面出願制度の前身であるPCT出願の枠組み導入時に、指定官庁が求める翻訳文の扱いは、“願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、要約書に記載した事項を過不足なく適正な日本語に翻訳したもの”という扱い、に沿う内容のものと、弊所では理解しています。
要するに、我が国を含めグローバルな特許制度の原則として、外国語を母国の言語(日本語)に翻訳する際の心構えとしては、第一に内容の(過不足のない)適正さが求められるのであって、逐語訳であっても、逐語訳でなくてもよいということです。
今回の改訂は、弊所を含めた関係者に、機械翻訳や生成AIの利用、特にポストエディット作業(機械翻訳をベースにした翻訳文の修正)との関連を含めて、非常に重要な指針を与えるものだと考えております。
特許庁内部の運用改正等についても、細部まで注視しながら、弊所は引き続き、お客様にとって最大限のサービス・サポートを追求して参ります。
※7月末に発行予定の当所英語版Newsletterにおいて、実際の翻訳の事例を含めたより詳細な解説を掲載いたしますので、是非そちらもあわせてご覧ください。
なお、本改訂に関する詳細は、以下の特許庁のサイトをご覧ください。
「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について | 経済産業省 特許庁